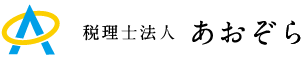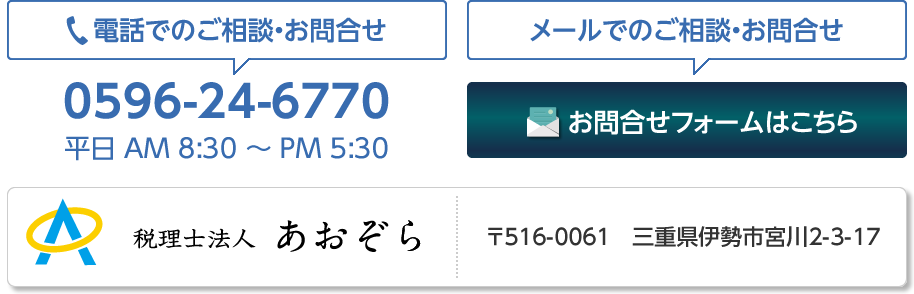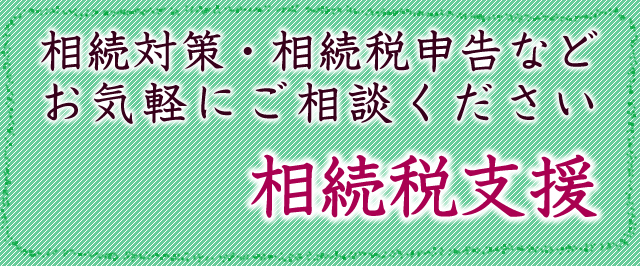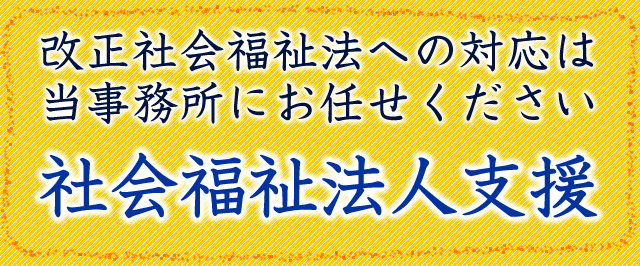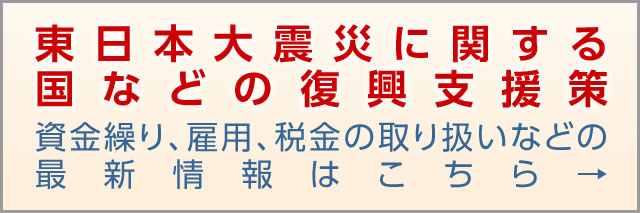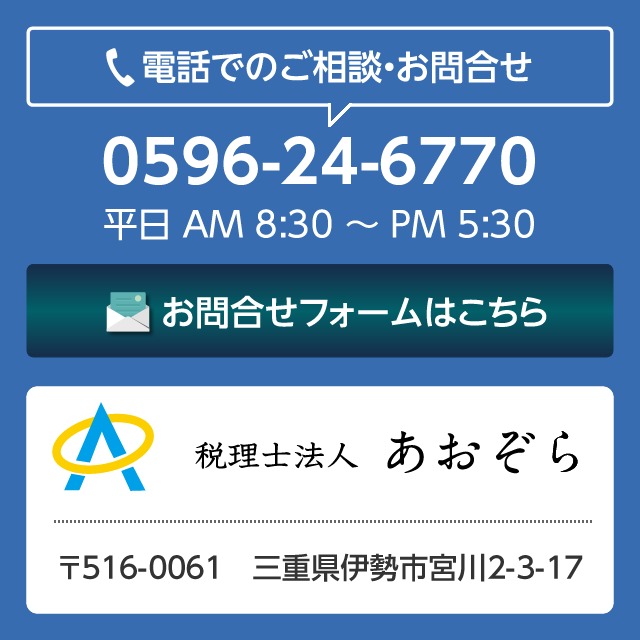毎月更新!時事コラム
最近の税に関するコトバ集
◆「早めに転職した人が不利で、ずっと会社に残った人が有利でいいのか」(8月7日、宮沢洋一自民党税制調査会長)――経済誌のインタビューで。最新の『骨太の方針』に盛り込まれた退職所得控除の見直しについて、「税調では以前から問題意識を持っているテーマだ」と述べ、「1つの会社に定年まで勤め上げるという労働慣行が変化しているなかで、税制をどう現状に合わせていくか。早めに転職した人が不利で、ずっと会社に残った人が有利でいいのか」と見直しの必要性を指摘した。「1つの会社に勤め続けることは悪いことではない」としながらも、年金制度の財政検証が行われる2024年に「退職金と年金を一緒に議論したほうがいい」との方向性を示した。
◆「マイナ保険証の見直しは大きな前進だ」(8月9日、松本吉郎日本医師会長)――定例会見で。来年秋に完全移行を目指していたマイナ保険証について、政府が紙の資格確認書を一律に交付することや、紙の保険証の有効期限を最長5年に延ばすなどの見直し案をまとめたことを前向きに評価した。日本医師会として「国民や患者の不安を払拭するため、資格確認書が必要とされる方全員に確実かつ迅速に交付される必要があると、これまでも言ってきた」と説明。その上で、「総点検の中間報告や再発防止といった国民の不安払拭のための政策パッケージと合わせて、国民・患者の不安払拭に向けて大きな前進であると理解している」と述べた。
◆「ガソリンからどれだけ税金取るんだよ、二重課税じゃん」(8月10日、タレントの大竹まことさん)――自身のラジオ番組で。ガソリンの値上がりが止まらず、8月9日にはレギュラーの1リットル当たりの価格が15年ぶりに180円を超えた。共演するアナウンサーの「ガソリンには石油・石炭税とか、環境にまつわる税金とか、温暖化にまつわる税金とか…。かつこれに消費税がかかります」との説明を聞いて、「結構すごいと思わないか。どれだけ税金取るんだよ。二重課税じゃない」と指摘した。さらに「庶民ひとりが納める税金とかは給料の48.5%とか言われてるわけでしょ。それじゃ暮らせないのに、それで働いてくださいって言われてもさ。誰か何か言ってくれる人はいないのか」と声を荒らげた。
気になるニュースのキーワード
燃料油価格激変緩和補助金(ガソリン補助金)
燃料油価格激変緩和補助金(ガソリン補助金)は、ガソリン価格の高騰を抑えるために、政府が石油元売り企業に対して支給する補助金のこと。コロナ禍の経済対策として2022年1月に始まり、ガソリン価格の抑制に一定の効果を挙げてきた。
現在の補助金は、ガソリンの全国平均価格がリッター170円を超えたときに、1リットル当たり5円を上限に元売り企業に補助金を支給するもの。一時期は上限額が35円まで拡充されたが、今年に入ってから上限額や補助率が徐々に引き下げられている。
経産省によれば、補助金によってガソリンの小売価格は最大で約40円抑制されたという。しかし今年1月の上限額切り下げ、5月の補助率引き下げという縮減によってガソリンの小売価格は徐々に上昇し、円安なども影響して現在では過去最高水準に迫る180円を突破している。これを受けて政府内では、現状9月末となっている補助金の期限を見直す動きも出てきつつある。
ただ昨年10月の財務省の調査では、補助金の全額が価格に反映されず、元売り業者やガソリンスタンドの利益確保のために使われていたケースが多数発覚した。またすでに補助金による公金支出は4兆円に上っていることから、低所得者に限定した給付金などでガソリン高に対応すべきとの声も出ている。
押さえておきたいIT用語
RPA
RPAは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略で、パソコンなどで行う事務系の単純作業を自動化し、コンピューターが代行することで業務効率化を図るものを指す。かつて業務の自動化といえば工場機械のオートメーションなどブルーカラーの業域がメインだったところを、RPAはホワイトカラーの単純作業を自動化するという点に特徴がある。日本語では「仮想知的労働者」と訳されることもある。
RPAの具体例としては、請求書発行、売上データの集計、エクセルにまとめられた情報の他システムへの登録・転記、送られてきたメールに添付されたファイルの振り分けなどが該当する。
業務のデジタル化において使われる言葉としては「AI」もあるが、AIは自ら判断して作業を行う一方、RPAはあらかじめ設定されたルールや基準に沿って単純作業を繰り返すという違いがある。いわばAIは「脳」だがRPAは「手」というわけだ。
また混同しがちな言葉として「マクロ」もあるが、マクロは『エクセル』など特定の製品内で作業を自動化するプログラムである一方、RPAは様々な製品にまたがって業務効率化を実現するサービスという違いがある。
2022年度末時点でRPAを導入した企業の割合は年商50億円以上の大企業で5割、50億未満の中小企業では3割程度といわれる。