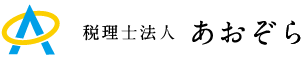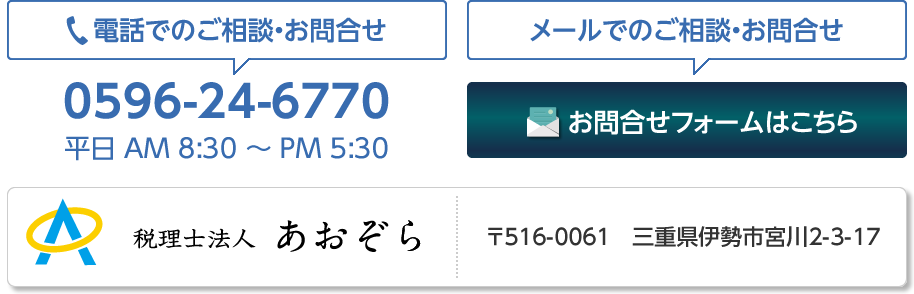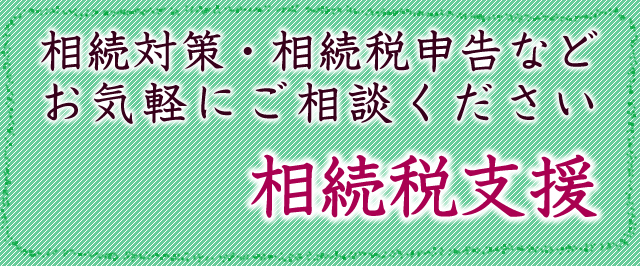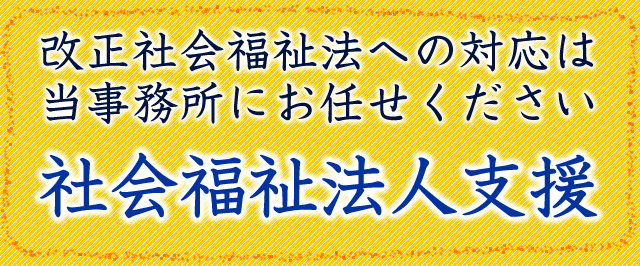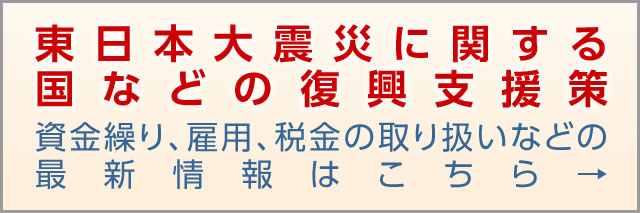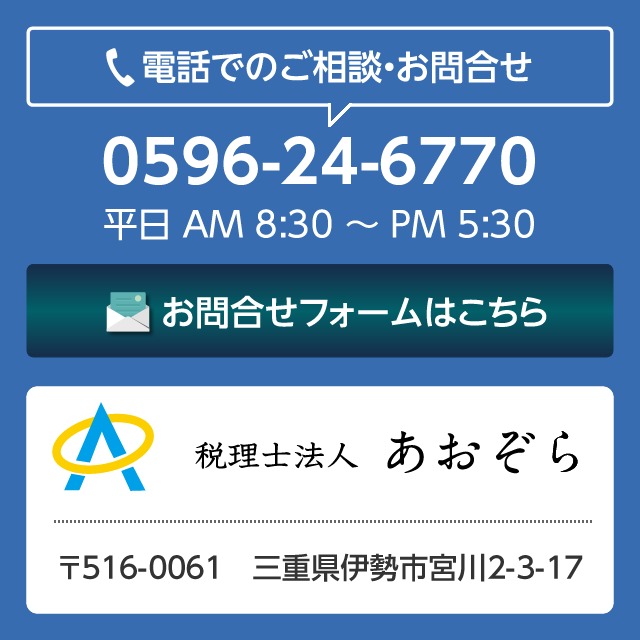毎月更新!時事コラム
最近の税に関するコトバ集
◆「インボイス制度でクールジャパンは終わる」(6月22日、「ガンダムシリーズ」で知られるアニメプロデューサーの植田益朗氏)――記者会見で。10月にスタートする消費税のインボイス制度について、「日本が世界に誇るアニメ・漫画文化をシュリンクさせる自殺行為だ」と中止を求めた。制度開始後は年収1千万円以下の免税事業者への発注分について仕入税額控除ができなくなるため、消費税分の負担を新たに発注者と受注者のどちらかが負う必要が生じる。そのため取引から免税事業者が淘汰されていくとの懸念がある。植田氏は「誰もが知る超大作でも多くの名もないクリエイターに支えられなければ生まれない」と指摘し、「インボイス制度で若手が減れば業界そのものが衰退する」と訴えた。
◆「無責任な防衛増税だ」(6月16日、立憲民主党の柴慎一参院議員)――参院本会議で。防衛予算の拡充を盛り込んだ特別措置法の採決を前に、「財源をどう確保するのか全く見通しが立っていない。このまま法案を通すのはあまりに無責任だ」と主張した。政府はロシアや中国などを念頭に有事のリスクが高まっているとして防衛力の抜本強化を掲げており、2027年までに年間予算をこれまでよりも4兆円ほど多い8.9兆円まで増やす計画だ。そのうち1兆円は増税で賄うとしているが具体案は固まっていない。なお特措法は、同参院本会議で自民・公明両党の賛成多数により可決、成立となった。
◆「子ども予算を確保するための増税は時期尚早」(6月14日、経済同友会の新浪剛史代表幹事)――記者会見で。「子ども予算」の拡充に向けた増税案が出ていることについて、「政府はすでに7.5兆円を投じており、現在は子育て政策の効果検証を行う段階のはず」と指摘した上で、「税の議論は時期尚早だ」との見解を示した。政府は「異次元の少子化対策」の実現に向けて予算倍増を目指すと発表している。新たに必要となる財源について経団連・日商といった経済団体や与党内からは「消費税など新たな税負担を検討すべき」との声が上がっているが、新浪氏は「子育て支援の前提としてまずは賃上げを優先すべき」とした上で、「ようやく高まりつつある賃上げの気運に増税で水を差すべきではない」と主張した。
気になるニュースのキーワード
商工中金の民営化
6月14日の参院本会議で可決・成立した「改正商工中金法」により、政府系金融機関の商工組合中央金庫(商工中金)の民営化が決まった。政府が保有する約46%の株式をすべて売却し、2年以内の民営化実現を目指すとしている。
商工中金は「中小企業の、中小企業による、中小企業のための金融機関」として1936年に国と中小企業組合の共同出資で設立された政府系金融機関だ。他の政府系金融機関が融資に特化している一方、商工中金には融資のみならず預金の受け入れや債券の発行といった民間金融機関と同様の金融サービスを行っているという特徴がある。災害や金融危機の際に国の利子補給で低利融資する「危機対応業務」も手掛けている。
政府は民営化により「半官半民の弊害を取り除く」としている。例えば企業への出資上限が現行の10%から民間金融機関と同等の100%にまで引き上がるため、株式取得による経営関与やM&A業者の子会社化など幅広い事業再生支援が可能となる。
ただ、民営化により利益追求が必要な立場になるため、融資審査がこれまでよりも厳しくなる懸念がある。金融機関の収益性を示す「預貸率(貸出残高÷預金残高×100)」は2022年9月末時点で105.6%と全金融機関の平均62.9%を大幅に上回っており、新たに貸し出す必要性も乏しい。
押さえておきたいIT用語
フェイクニュース
フェイクニュースとは、オンライン上で発信・拡散される偽りの情報のこと。もともとは単なるいたずらやアクセス数稼ぎを狙って発信されるものがほとんどだったが、ブログやSNSなどのソーシャルメディアの普及に伴い、近年は組織的な世論工作や差別の扇動など悪質な目的のために用いられ社会問題となっている。
社会問題として注目を浴びるようになったきっかけは2016年の米大統領選挙だ。選挙を前に「ローマ法王がトランプ氏を支持、世界に衝撃」といった情報がSNSなどオンライン上で拡散され一部の人々の投票行動を左右したが、実際にはフェイクニュースだった。この選挙では最終的にトランプ氏が当選したものの、「フェイクニュースで当選したに過ぎない」との批判が出るなど禍根を残す結果となった。
日本国内でもコロナ禍でフェイクニュースが蔓延した。「26~27℃のお湯を飲むのが有効」「漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を飲むと回復効果がある」といったニセのコロナ感染対策がツイッターやラインなどのSNS上に相次いで投稿された。
国際大学(新潟県魚沼市)の研究によると、人々の75%は自力でフェイクニュースを見抜けないという。フェイクニュース対策については総務省の有識者会議が議論を続けているが、表現の自由の観点から規制は難しいのが実情だ。